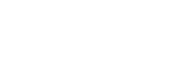犬の乾燥肌が増えている理由― 現代の暮らしと犬の皮膚トラブルの関係 ―
飼い主さんが不安なときに、まず役立つ情報を届けるためにまとめてみました。心配な症状が続く場合は、動物病院へご相談ください。
1. 乾燥肌のサインとは?
犬も皮膚が乾燥すると、次のような変化が見られることがあります。
- フケが出る
- 肌をしきりにかく・舐める
- 赤みやカサつきが目立つ
- 被毛がパサつく
- 触ったときに皮膚がざらつく
これらは皮膚バリアが弱っているサインと考えられています。アレルギーや感染症が背景にある場合もあるため、注意が必要です。
2. 犬の皮膚はヒトよりずっと弱い
犬の皮膚は、角質層が人の約1/3〜1/5ほどの厚みと言われており、水分が失われやすい構造をしています。そのぶん、外からの刺激も受けやすく、
- 乾燥しやすい
- 少しの環境変化でもトラブルにつながりやすい
という特徴があります。
3. 室内飼いが増えたことで乾燥しやすくなっている
現代はほとんどの犬が室内で過ごしています。快適な環境のはずが、実は乾燥肌の原因にもなりえます。
代表的な例としては、次のようなものがあります。
- エアコン暖房による空気の乾燥
- 冷暖房の使用時間が長く、一年を通して乾燥しやすい室内環境になりやすい
- フローリングなどの床材で皮脂が奪われやすい生活
このように、季節を問わず室内は犬の皮膚にとって乾燥しやすい環境になりやすいと言えます。

4. 間違ったケアが乾燥を悪化させることも
皮膚を清潔に保つことは大切ですが、ケアの仕方によっては乾燥を強めてしまうこともあります。
- 頻繁なシャンプーによる洗いすぎ
- ゴシゴシと強くこする洗い方
- ドライヤーの熱を近距離で長時間あてる
こうしたケアは、皮膚を守るために必要な皮脂まで取り除いてしまい、乾燥を悪化させる一因になると考えられています。乾燥が気になるときほど、「優しく」「必要以上に落としすぎない」という意識が大切です。
5. 食事やアレルギー体質も関わる
皮膚のうるおいを保つためには、日々の食事も関係していると考えられています。
- たんぱく質
- 必須脂肪酸(オメガ3・オメガ6など)
- ビタミン類
といった栄養は、皮膚や被毛をつくる材料になります。
また、アレルギー体質の犬は乾燥しやすい傾向があるとも言われています。皮膚トラブルが繰り返し起きる場合は、体質やアレルギーが関係している可能性もあります。
6. 年齢による変化にも注意
年齢とともに皮脂分泌が変化し、シニア期になると皮膚の乾燥が目立ちやすくなるとされています。若い頃と同じケア方法では合わなくなるケースもあり、
- シャンプーの頻度
- お湯の温度やドライヤーの当て方
- 日々のブラッシングの仕方
などを見直すタイミングにもなります。
7. 季節ごとのリスクの違い
犬の乾燥肌は一年を通して起こりえますが、季節によって注意したいポイントが少しずつ変わります。
| 季節 | 乾燥肌リスク | 主な理由 |
|---|---|---|
| 冬 | 高い | 空気の乾燥に加え、暖房による湿度低下 |
| 夏 | やや高い | エアコン使用による室内の乾燥 |
| 梅雨〜高温期 | 低〜中 | 乾燥よりも、湿気による雑菌トラブルに注意 |
このように、同じ「皮膚トラブル」でも、季節によって背景が変わることがあります。一年を通して状況を見ながらケアの方法を調整していくことが大切です。
8. 自宅でできる乾燥対策
少しの工夫でも、乾燥による負担を減らす手助けになります。
- 部屋の湿度を保つために、加湿を意識する
- ブラッシングで皮膚の血行を促し、皮脂が行き渡るようにする
- 入浴後はしっかりタオルドライをしてからドライヤーを使う
- ドライヤーは肌から距離をあけ、弱めの温度で当てる
「やりすぎない」「強くやりすぎない」という意識をもつだけでも、皮膚への負担は変わってきます。
9. こんなときは病院へ
自宅でのケアを続けても次のような状態が見られるときは、自己判断に頼らず、動物病院で相談することが推奨されています。
- 赤み・かゆみが長引く
- フケや脱毛が広がっている
- 皮膚に傷やただれが見られる
- 愛犬が落ち着かず、ずっと不快そうにしている
皮膚のトラブルは、早めに対処した方が悪化を防ぎやすいと言われています。「おかしいな」と感じたときは、早めに受診するのが安心です。
まとめ
現代の犬は、室内環境やケアの方法、体質や年齢など、さまざまな要因が重なって乾燥肌になりやすい状況にあると考えられています。
いつもと様子が違うと感じたときは、生活環境やケアの仕方を少し見直してみるとともに、気になる状態が続く場合は動物病院に相談してみてください。
本記事は参考情報としてお役立ていただくことを目的としています。心配な症状が改善しない場合や、不安がある場合は、必ず獣医師にご相談ください。